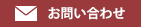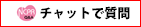制度の概要
新生児蘇生法委員会が管理運営する講習事業制度の概要は次の通りです。 尚、下記の内容が修正されることもありますので、予めご承知おき下さい。 不明な点がございましたら新生児蘇生法普及事業事務局までお問い合わせ下さい。
講習会
| 分類 | 主催者 | 開催場所 | コース名 |
|---|---|---|---|
| 主催講習会 | 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法委員会 |
常設:トレーニングサイト
他:特別会場として指定 |
インストラクターコース フォローアップコース |
| 公認講習会 | (1)本制度の認定を受けたインストラクター資格者 (2)前項(1)を開催責任者にしている自治体・医療関係団体・医療機関、等 |
主催者にて指定 | 専門コース 一次コース 病院前コース スキルアップコース |
| 分類 | コース名 | 講習内容 | 受講資格 | 講習時間 | 合否判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催講習会 | インストラクターコース | インストラクターの養成を目的に臨床知識・実技実習に関する指導法の習得 | (1)「専門コース」修了認定者 (2)最新のガイドラインを履修済みであること (3)公認講習会においてインストラクター補助実績が2回以上あること(うち1回は専門(A)コースであること) (4)専門コースインストラクター1名以上の推薦があること |
5時間半 | あり | 詳しくは こちら |
| 病院前インストラクターコース | 病院前コースのインストラクター養成を目的に、病院前新生児蘇生法の知識・実技実習に関する指導法の習得 | (1)「専門コース」または「病院前コース」または「一次コースインストラクター」の修了認定者 (2)最新のガイドラインを履修済みであること (3)公認「病院前コース」においてインストラクター補助実績が2回以上(一次コースインストラクターは1回以上)あること (4)専門コースインストラクター1名以上の推薦があること |
5時間半 | あり | 詳しくは こちら |
|
| フォローアップコース | インストラクションの質の維持を目的とした、NCPR講習会における指導法の復習コース | インストラクター修了認定取得者 | 3時間半 | なし | 詳しくは こちら |
|
| 公認講習会 | 専門コース | 気管挿管、薬物投与を含めた「臨床知識編」「実技編」で構成される高度な新生児蘇生法の習得 | 周産期医療機関の医師・看護師・助産師・救急救命士等 | 5時間 | あり | 詳しくは こちら |
| 一次コース | 気管挿管、薬物投与を除く「臨床知識編」「実技編」で構成される基本的な新生児蘇生法の習得 | 一般の医師・看護師・助産師・初期研修医・救急救命士・医学生・看護及び助産学生等 | 3時間 | あり | 詳しくは こちら |
|
| 病院前コース | 医療施設外での出生を想定した新生児蘇生法の習得 | 救急救命士・救急隊員・消防吏員等 | 3時間 | あり | 詳しくは こちら |
|
| スキルアップコース | 蘇生技術の質の維持を目的とし「講義」「手技実習」「シナリオ実習」で構成された復習コース | 修了認定取得者 | 3時間 | なし | 詳しくは こちら |
※ すでにインストラクターの資格をお持ちの方へ・・・
公認講習会を開催される場合は、本委員会への「事前公認申請手続き」が必要です。
これらの記述については、「インストラクター・主催者の専用ページ」をお読み下さい。
認定
1 専門コース・一次コース・病院前コースの講習会当日に行われる筆記試験に合格し、合格通知書発行日から3ヶ月以内に所定の認定申請手続きを行って頂きます。
2 手続きに必要な書類、その他に制約事項がありますので、ご注意下さい。詳しくはこちら
| 職種 | 区分 | 認定料 |
|---|---|---|
| 医師 | 日本周産期・新生児医学会 会員 |
5,500円 |
| 日本周産期・新生児医学会 非会員 |
11,000円 | |
| 助産師、看護師、その他コ・メディカル | 周産期医療従事者 | 5,500円 |
| 救急救命士・救急隊員・消防吏員等 | 5,500円 | |
| 学生 | 医学、看護学、助産学等 | 5,500円 |